注文住宅の諸費用はいくら?内訳ごとの相場や抑えるための方法を解説

「注文住宅の諸費用はいくらかかる?」
「注文住宅の諸費用には何が含まれる?」
注文住宅の資金計画を立てるうえで、上記のように悩む方は多いのではないでしょうか。
注文住宅の諸費用には、土地や住宅を取得する際の手続き費用や税金など、さまざまな項目があります。項目ごとに支払いのタイミングが異なるため、いつ何がかかるかを把握しておくことが大切です。
本記事では、注文住宅でかかる諸費用の相場や内訳を解説します。注文住宅の諸費用について調べている方は、ぜひ参考にしてください。
この記事でわかること
- 注文住宅の諸費用の相場
- 注文住宅の諸費用の内訳
- 注文住宅の諸費用を抑える方法
THINK HAUSでは、諸費用以外の注文住宅の費用についても解説しています。家づくりにかかる費用や資金計画の立て方を動画も含めて解説しているため、家づくりがはじめての方の参考になるでしょう。
家の資産価値やライフサイクルコストについても紹介しているので、将来の住み替えや維持管理を見据えた資金計画が立てやすくなります。会員登録は以下から無料で行えるため、お気軽にご利用ください。
もくじ
注文住宅の諸費用とは「土地代や建物の本体価格以外でかかる費用」のこと

注文住宅にかかる諸費用とは、土地代や建物の本体価格以外でかかる費用のことです。具体的には、土地の取得から住宅の引き渡しまでにかかる手続き費用や税金などを指します。
注文住宅の諸費用は、項目によって支払いのタイミングが異なります。そのため、いつ払うのか、いくらかかるのかを事前に把握して資金を用意しておくことが大切です。
後から支払いで苦労しないためにも、注文住宅を建てる際は、諸費用も含めてゆとりのある資金計画を立てましょう。
注文住宅の諸費用の相場は?

注文住宅の諸費用の相場目安は、土地と建築費の合計金額の約10%といわれています。
ただし、実際の諸費用は、住宅の購入方法や必要な手続きによって大きく差があります。相場はあくまでおおよその費用を把握する際の目安とし、条件次第でかかる諸費用が異なることを押さえておきましょう。
たとえば、総額3,000~6,000万円の注文住宅では以下の金額の諸費用がかかる計算になります。
| 注文住宅の建築にかかる費用の総費用 | 諸費用の金額目安 |
|---|---|
| 3,000万円 | 300万円 |
| 4,000万円 | 400万円 |
| 5,000万円 | 500万円 |
| 6,000万円 | 600万円 |
【内訳一覧】注文住宅にかかる諸費用の項目

注文住宅にかかる諸費用の項目は以下の通りです。
| 支払いのタイミング | 項目 |
|---|---|
| 土地取得時 | ・印紙税 |
| ・固定資産税精算金 | |
| ・仲介手数料 | |
| ・登記費用 | |
| ・不動産取得税 | |
| 建物の建築時 | ・設計図書作成費 |
| ・印紙税 | |
| ・建築確認の申請手数料 | |
| ・地鎮祭費用 | |
| ・登記費用 | |
| ・不動産取得税 | |
| 住宅ローン利用時 | ・印紙税 |
| ・ローン保証料 | |
| ・融資事務手数料 | |
| ・登記費用 | |
| その他注文住宅にかかる諸費用 | ・火災保険料および地震保険料 |
| ・引っ越し費用や家具の購入費用 |
注文住宅の諸費用には、大きく分けて上記の4種類があります。
なお、すでに土地がある状態で注文住宅を建てる場合は土地代がかからないため、土地取得時の諸費用は発生しません。
各項目の詳しい内容や相場については、以下で解説します。
土地取得時にかかる諸費用の内訳と相場

土地取得時にかかる諸費用には、主に以下の5つがあります。
それぞれの内容や目安となる相場について詳しく解説します。
1. 印紙税
土地の売買契約書は、印紙税法上の課税文書に該当するため、契約時に印紙税が課税されます。
印紙税額は、契約金額によって以下のように一律の金額に決められています。
| 契約金額 | 本則税額 | 軽減措置適用後の税額 |
|---|---|---|
| 100万円超~500万円 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超~1,000万円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超~1億円 | 60,000円 | 30,000円 |
2027年3月31日までに作成された契約書は軽減措置の対象です。実際の契約では、契約金額に応じた印紙税額を売主と買主で折半して納めます。
※参照:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
2. 固定資産税精算金
固定資産税の課税対象となる年度途中に土地を購入した場合は、売主に対して固定資産税の精算金を支払う必要があります。一般的には、固定資産税の年額を日割り計算し、購入した月以降の分の固定資産税を買主が負担します。
固定資産税の課税対象期間は、1月1日~12月31日です。たとえば、8月に土地を購入した場合は、8月~12月分に相当する固定資産税を日割り計算して精算することになります。
3. 仲介手数料
不動産会社を介して土地を購入する場合は、不動産会社に支払う仲介手数料が発生します。
不動産取引の仲介手数料は、国土交通省の告示により、以下の通り上限が定められています。
| 200万円以下 | 契約金額×5.5% |
| 200万円超~400万円以下 | 契約金額×4.4% |
| 200万円超~400万円以下 | 契約金額×3.3% |
価格が800万円以下の宅地については、特例で30万円×1.1倍の金額が上限です。
※参照:国土交通省「不動産取引に関するお知らせ」
不動産取引の仲介手数料は計算が複雑なため、以下の速算式で求められることが一般的です。
不動産の仲介手数料=契約金額×3%+6万円
たとえば土地の価格が1,000万円なら、1,000万円×3%+6万円=36万円の仲介手数料がかかる計算になります。
4. 登記費用
土地の購入後は、土地の所有権移転登記を行うための費用がかかります。
所有権移転登記とは、不動産の所有者名義を変更する手続きのことです。
所有権移転登記を行う際は、地域を管轄している法務局または法務支局に登録免許税を納める必要があります。所有権移転登記の登録免許税の金額は、土地の固定資産税評価額の2%です。
ただし、2026年3月31日までの登記は軽減税率の対象となり、固定資産税評価額の1.5%に登録免許税額が引き下げられます。
さらに登記手続きを司法書士に代行してもらう場合は、3~10万円前後の依頼料もかかります。
※参照:国税庁「登録免許税の税額表」
※参照:国税庁「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」
5. 不動産取得税
土地を取得すると、固定資産税評価額の4%に相当する不動産取得税が課税されます。
ただし、2027年3月31日までに取得した土地については、3%の軽減税率の適用対象です。土地が住宅用地、または住宅の建築に適していると認められた場合は、固定資産税評価額を2分の1にする軽減措置も受けられます。
さらに、一定の要件を満たした場合は控除の特例が適用され、以下2つのうち高いほうの金額が税額から差し引かれます。
- 4,500,000円
- 土地1㎡あたりの固定資産税評価額×住宅の床面積×2(1戸200㎡が上限)×3%
※参照:総務省「地方税制度|不動産取得税」
※参照:東京都主税局「不動産取得税」
建物の建築時にかかる諸費用の内訳と相場

建物の建築時にかかる諸費用の内訳は、以下の通りです。
それぞれ詳しく解説します。
1. 設計図書作成費
注文住宅の建築時は、建物の間取りやデザインを設計するための設計図書作成費がかかります。設計図書作成費の金額は、建物本体の建築費の10%程度が相場といわれています。
ただし、ハウスメーカーでは設計図書作成費が本体工事費用に含まれることが多いです。工務店や設計事務所など、業者のタイプによって扱いが異なるため、事前に確認しておきましょう。
2. 印紙税
工事前の発注契約で交わす工事請負契約書も、課税文書なので印紙税が課せられます。工事請負契約書の印紙税額は、先ほど解説した土地の売買契約書の印紙税額と同じで、以下のとおりです。
| 契約金額 | 本則税額 | 軽減措置適用後の税額 |
|---|---|---|
| 100万円超~500万円 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超~1,000万円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超~1億円 | 60,000円 | 30,000円 |
同様に2027年3月31日までに作成された契約書については、軽減税率の対象になります。
※参照:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
3. 建築確認の申請手数料
注文住宅の建築時は、建物が建築基準法や条例に適合しているかを確認するための建築確認申請を行う必要があります。建築確認を行うタイミングは、設計後と住宅完成後の2回です。
建築確認の申請手数料は、自治体や住宅の床面積によって金額が異なるため、ハウスメーカーに確認してみるとよいでしょう。
4. 地鎮祭費用
注文住宅を新築する場合は、着工前に地鎮祭を行い、工事の安全や無事を祈願することが一般的です。その際、神主への謝礼として初穂料やお車代などの費用がかかります。
地鎮祭の初穂料の金額は、3~5万円程度が相場です。
5. 登記費用
新築の注文住宅を取得すると、土地の所有権移転登記とは別に、家屋の所有権保存登記を行う必要があります。所有権保存登記の登録免許税額は、固定資産税評価額の0.4%です。
なお、新築住宅の場合は、まだ固定資産税評価額が決まっていないため、住宅完成時に法務局が認定した不動産価額が基準になります。また、2027年3月31日までに新たに居住用家屋を取得する場合は、税率の軽減措置が受けられます。
軽減措置の対象となる住宅の条件と、軽減税率は以下の通りです。
| 住宅の条件 | 軽減税率 |
|---|---|
| マイホームを新築、または建築後未使用の住宅用家屋を取得した場合 | 0.15% |
| 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅を新築、または建築後未使用の住宅用家屋を取得した場合 | 0.1% |
所有権保存登記の手続きも司法書士に依頼する場合は、別途依頼料がかかります。所有権保存登記の司法書士報酬額は、1.5万~6万円程度が相場の目安といわれています。
※参照:国税庁「登録免許税の税額表」
※参照:国税庁「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」
6. 不動産取得税
住宅の取得後は、土地とは別に不動産取得税を納める必要があります。
住宅における不動産取得税の税率は土地と同じ3%ですが、固定資産税評価額を2分の1にする軽減措置がありません。ただし、代わりに固定資産税評価額から1,200万円を差し引く控除の特例が利用できます。
新築する住宅が長期優良住宅の場合は、控除額が1,300万に増額されます。
住宅ローン利用時にかかる諸費用の内訳と相場

住宅ローン利用時にかかる諸費用の内訳は、以下の通りです。
それぞれ詳しく解説します。
1. 印紙税
住宅ローンを利用する際に交わす貸借契約書にも、印紙税が発生します。貸借契約書の印紙税額は、土地の売買契約書と建築時の工事請負契約書と同じです。
| 契約金額 | 本則税額 | 軽減措置適用後の税額 |
|---|---|---|
| 100万円超~500万円 | 2,000円 | 1,000円 |
| 500万円超~1,000万円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 5,000万円超~1億円 | 60,000円 | 30,000円 |
2027年3月31日までに作成された貸借契約書についても同様に、軽減税率の対象となります。
※参照:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
2. ローン保証料
ローンの保証を保証会社に依頼する場合は、ローン保証料がかかります。ローン保証とは、住宅ローンの契約者がなんらかの理由で返済できなくなった場合に、本人に代わって一括弁済してくれる保証です。
ローン保証料の支払い方法には、ローン契約時に全額支払う外枠方式と、金利に上乗せする内枠方式の2つの方法があります。それぞれの方法におけるローン保証料の相場は以下の通りです。
| 支払い方法 | 保証料の相場 |
|---|---|
| 外枠方式 | 借入金額の約2% |
| 内枠方式 | 金利の0.2%を上乗せした金額 |
内枠方式は、保証料をローンの借入額と一緒に分割して支払うため、自己資金の負担を軽減できます。ただし、金利にローン保証料が上乗せされ、最終的な返済額が増えることに注意が必要です。
3. 融資事務手数料
住宅ローンを利用する際は、融資実行費用として融資事務手数料がかかります。融資事務手数料は、融資金額に関係なく一律で設定されている場合もあれば、融資金額に一定の割合をかけるケースもあります。
定額型の場合、融資事務手数料は3〜5万円程度が相場です。定率型は、融資額の1〜3%が目安になります。
4. 登記費用
住宅ローンを利用して住宅を取得すると、金融機関の要請により建物に抵当権が設定されます。抵当権を設定するためには抵当権設定登記が必要となり、融資金額の0.4%に相当する登録免許税が課税されます。
ただし、2027年3月31日までに行われた自身の居住用住居の抵当権設定登記は、軽減措置の対象です。抵当権設定登記の軽減措置が適用されると、税率が0.1%に引き下げられます。
また、抵当権設定登記においても司法書士を介して行う場合は、別途司法書士報酬の支払いが必要です。抵当権設定登記の司法書士の報酬相場は、2〜5万円です。
※参照:国税庁「登録免許税の税額表」
※参照:国税庁「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」
その他注文住宅にかかる諸費用の内訳と相場

注文住宅の建築では、土地取得時、建物の建築時、ローン利用時以外にも、以下のような諸費用がかかります。
注文住宅の資金計画を立てる際は、これらの費用も含めて予算を考えておく必要があります。
1. 火災保険料および地震保険料
注文住宅の建築にあたって火災保険や地震保険に加入する場合は、加入時に保険料がかかります。
保険料の金額は、保険会社や保証内容によって異なります。保険会社によっては、火災保険と地震保険がセットになっているものもあるため、内容をよく確認しましょう。
また、住宅ローンの利用時は、火災保険への加入が必須要件となっているケースがほとんどです。地震保険への加入は任意のため、必要に応じて検討しましょう。
2. 引っ越し費用や家具の購入費用
注文住宅を建てる際は、住宅の完成後の引っ越しにかかる費用や家具の購入費用も考えておく必要があります。
引っ越し業者の利用料金は、移動距離や荷物の量、時期によって変動します。引っ越し時期が決まっている場合は、一度見積もりをとっておくとよいでしょう。
家具や家電は、必要なものをリストアップしてだいたいの金額の目星をつけておくと、予算が立てやすくなります。
住宅の建て替えで仮住まいをする場合は、引っ越し費用と仮住まいの家賃も考慮しましょう。
注文住宅の諸費用を抑える方法

注文住宅の諸費用を抑える方法は、以下の4つです。
それぞれ詳しく解説します。
1. 不動産会社やハウスメーカーが所有している土地を選ぶ
なるべく注文住宅の諸費用を抑えたいなら、不動産会社や建築会社が所有している土地を選ぶとよいでしょう。
不動産会社やハウスメーカーによっては、自社で保有している土地を直接販売しており、仲介手数料が不要になるケースがあります。数万~数十万の仲介手数料をカットできるため、土地取得時にかかる諸費用を大幅に抑えられるでしょう。
ただし、不動産会社などが保有する土地には建築条件付きのものも多く、条件によっては希望の住宅を建てられない可能性があります。そのため、希望の住宅を建てられる土地かどうか、担当者としっかり相談したうえで検討することが大切です。
旭化成ホームズの不動産ネットワーク「ACE」では、理想のマイホームを建てるための土地探しをサポートしています。旭化成ホームズ自社保有の土地や分譲地も複数あるため、仲介手数料なしでの提案が可能です。
また、仲介物件であっても、土地と住宅をセットで考えて希望の土地を探すため、理想の家づくりが叶えられます。住宅に適した土地探しを土地の専門家が手厚くサポートしているので、土地選びでお困りの方はぜひご相談ください。
2. ローン保証の内容を見なおす
ローン保証の内容を見なおすことでも、注文住宅の諸費用を抑えられる可能性があります。
一般的な住宅ローンでは、団体信用生命保険への加入が契約の条件となっています。そのため、すでに加入している生命保険がある場合は保障内容が重複するかもしれません。住宅ローンを借りる場合は、生命保険の見直しもセットで検討すると安心です。
ハウスメーカーによっては、ライフプランのシミュレーションを行ってくれることもあるため相談してみるとよいでしょう。
なお、ローン保証は、保証料なしのフラット35を利用することでも抑えられます。
3. 補助金制度を利用する
注文住宅の諸費用の負担は、公的機関で行われている補助金制度を利用することでも抑えられます。たとえば、省エネ性能が高い住宅やZEH住宅、長期優良住宅などを建てる場合は補助金制度を活用できる可能性があります。
2025年1月現在、新築の注文住宅で利用できる補助金制度は、以下の2つです。
- 子育てグリーン住宅支援事業
- サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)
※参照:国土交通省「令和6年度支援事業一覧」
諸費用そのものを抑えられるわけではありませんが、費用全体の負担が減るため、資金に余裕が出ます。資金に余裕が生まれた結果、設備や内装の選択肢が広がり、理想のマイホームづくりができるようになるでしょう。
自治体ごとに独自の補助金制度を設けている場合もあるため、自治体の公式サイトなどで確認してみてください。
4. 引っ越しは繁忙期を避けて行う
繁忙期を避けて引っ越しを行うことも、費用を抑える方法の一つです。
引っ越し作業を業者に依頼する場合、シーズンによっては繁忙期に入り、通常の数倍の料金がかかることがあります。とくに引っ越しが多くなる3~4月に料金が高騰しやすい傾向です。
引っ越し時期が定まっていない場合は、引っ越しの繁忙期を避け、料金が安い時期を狙ってスケジュールを組んでみるとよいでしょう。
専門家コメント
注文住宅の諸費用はローンに組み込むこともできます。金融機関が提供している住宅ローンの中には、諸費用を融資の対象にしているものもあるためです。なるべく融資項目が多いローンを利用することで、自己資金の負担を減らせるでしょう。
たとえば以下の注文住宅の諸費用は、ローンに組み込める可能性があります。
- 印紙税
- 登記費用
- 仲介手数料
- 火災保険料および地震保険料
- 融資事務手数料
- ローン保証料
また、「諸費用ローン」や、住宅ローンの融資実行前の費用を一時的に融資する「つなぎ融資」を利用することも方法の一つです。ただし、これら2つのローンは、金利が高めに設定されているため、最終的に返済額が増えることに注意が必要です。
諸費用を抑えることでも自己資金の負担を軽くできるため、のちの返済で苦しくならないよう、ローンの利用は慎重に検討しましょう。

注文住宅の諸費用の相場や内訳を知って資金計画を始めよう

注文住宅の諸費用の金額目安は、土地代と建物建築費の合計費用の10%程度です。
ただし、あくまで目安であり建物や土地の条件次第で変動する可能性があるため、ハウスメーカーに必ず見積もりを確認してください。
不動産取得税などの税金は、法改正により税率が変更されることもあります。また、土地の状況次第で急に増加することもあるため、多めに見積もっておくとよいでしょう。
ヘーベルハウスの情報ナレッジサイト「THINK HAUS」では、諸費用をはじめとした家づくりにかかる費用と資金計画のポイントなどを、初心者にもわかりやすい豊富な図解つきで解説しています。
ヘーベルハウスの豊富な実例や10問に答えるだけで理想の間取りがわかるシミュレーターなどもご用意しているので、理想のマイホームづくりを進めるのに役立つでしょう。
「情報収集していてもなかなか資金計画がうまく立てられない…」とお悩みの方は、ヘーベルハウスへお気軽にご相談ください。資金計画のプロも多数在籍しており、お客様の資金の悩みや要望に応じたマイホームのご提案が可能です。
また実際に住宅展示場を見学してみると、シミュレーションやネットなどの情報からでは得にくいリアルなイメージを把握しやすいです。展示場でも資金計画を含めた相談に対応しているので、ぜひ来場予約のうえお越しください。
家づくりお役立ちコンテンツ
- 注文住宅のメリット・デメリットとは?
建売住宅や分譲住宅とどう違う? - 注文住宅のローンを組むには?
手続きの流れを徹底解説! - 【坪数別】注文住宅の間取り例をご紹介!
シミュレーションは可能? - ZEH(ゼッチ)とは?
ZEHのしくみをご紹介! - 注文住宅の相場はいくら?
平均的な費用、建築費以外にかかる付帯
工事費や諸費用もふまえて資金計画を - 注文住宅がもたらす嬉しいメリットとは?
デメリットもおさえて
快適な家づくりを - 【実例①】実例とともにご紹介。
住む人を豊かにする
ヘーベルハウスの家づくり - 【実例も紹介】3階建て住宅を快適に過ごすための間取りとは?
知っておくべき魅力点&注意点 - 二世帯住宅がもたらすメリットとは?
快適に住むために知っておくべき
3つの間取りスタイル - 狭小住宅ならではの贅沢空間!
狭さを感じさせない
夢の間取りのコツとは? - 注文住宅の間取りは
どうやって決める?
家づくりで取り入れたい
人気の間取りアイデアを紹介 - 戸建て住宅とは
メリットとほかの住宅との違い
種類や家づくりにおけるポイントまで
分かりやすく解説! - 三階建ての家づくりを
柔軟に楽しくする
間取りアイデア集 - 二世帯住宅の間取りに悩んだときの
おすすめとは?
失敗事例に潜む注意点も詳しく解説 - 注目されつつある平屋の家。
平屋のメリット・デメリットを知って
理想的な暮らしを叶える - 建て替えするなら知っておきたい費用のこと
リフォームや住み替えと
迷ったときの判断ポイント - アウトドアリビングで充実した“おうち時間”を…!
アウトドアリビングのメリットや
後悔しないためのポイントをご紹介 - 注文住宅ができるまで
情報収集から完成までの
基本の流れを知って始める家づくり - 家づくりの流れ12ステップ!
何から始めるかや
期間をわかりやすく解説 - 家の構造6種類の特徴を解説!
5つの工法や選び方の
ポイントも紹介 - 家を建てる際の基礎知識を解説!
費用、流れ、依頼先など
注意点を紹介 - 家づくりの初心者向けガイド!
流れや費用の目安、後悔しないための
ポイントなどをすべて解説 - 家の外観は何で決まる?
デザインの種類や実例、
決め方のポイントを紹介 - 注文住宅で人気の間取り10選!
後悔しない決め方の
ポイントも紹介 - 家の内装を決める3つのポイントを解説!
おしゃれにする方法や事例も紹介 - 注文住宅を大阪に建てる費用はいくら?
人気エリアと土地代の相場も紹介 - 注文住宅の相場をエリア別・坪数別で紹介!
土地あり・なしでいくら変わるかも解説 - 注文住宅の平屋のメリット・デメリット!
相場や間取り事例を紹介 - 愛知で注文住宅を建てたい!
費用の相場や
年収いくらで建てられるかを解説 - 注文住宅を千葉県に建てる費用相場は?
依頼先の種類や
選び方も解説 - 群馬県で注文住宅を建てる費用相場は?
気候に合わせた住宅の特徴も紹介 - 注文住宅を埼玉県に建てる費用は?
人気エリアやローンの金額も紹介 - 注文住宅の坪単価とは?
相場や費用を比較する際の
注意点を解説 - 家のローンはいくらにするといい?
年収別の借入可能額の目安や利用の
ポイントを解説 - 注文住宅を東京都に建てる費用の相場は?
9つの人気のエリアと業者の
選び方も紹介 - 注文住宅の玄関のおしゃれな事例8選!
よくある失敗例や回避するための
ポイントも紹介 - 注文住宅で人気のキッチンの種類は?
7つのおしゃれな事例や決め方の
ポイントを紹介 - 注文住宅のリビングづくりで
重視すべき6つのポイント!
おしゃれにするための
コツや実例を紹介 - 注文住宅のおしゃれなガレージの実例を紹介!
メリット・デメリットも解説 - 注文住宅の見積もりをとりたい!
依頼する流れや注意点を解説 - 注文住宅の諸費用はいくら?
内訳ごとの相場や
抑えるための方法を解説 - 注文住宅は相談先選びが重要!
相談内容や事前に準備することを
紹介 - 注文住宅の窓の種類とは?
選び方のポイントや
おしゃれな実例も紹介







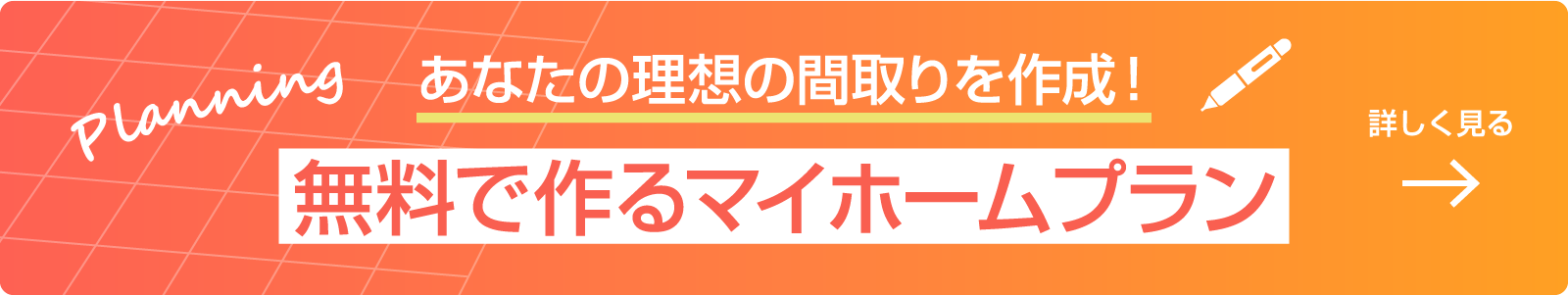
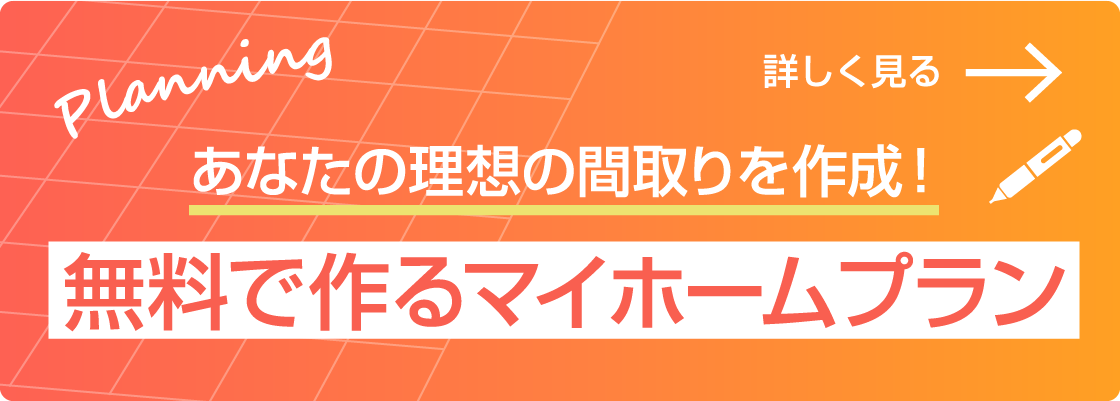
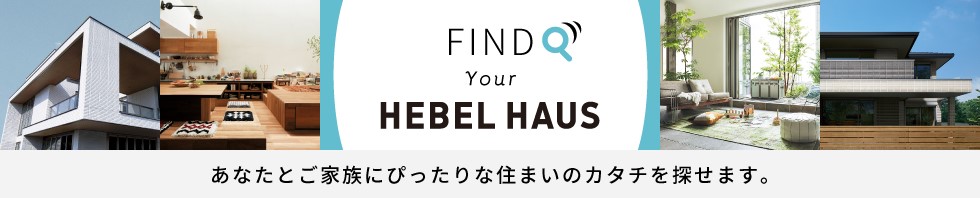





専門家コメント
注文住宅の諸費用が高くなる例としては、以下のようなケースが挙げられます。
基本的に土地も含めた計画だったり、建物が大きかったりする場合に高くなるケースが多いです。
このように諸費用は、土地の状況や契約内容によって追加でかかる可能性もあるため、多めに見積もっておくとよいでしょう。