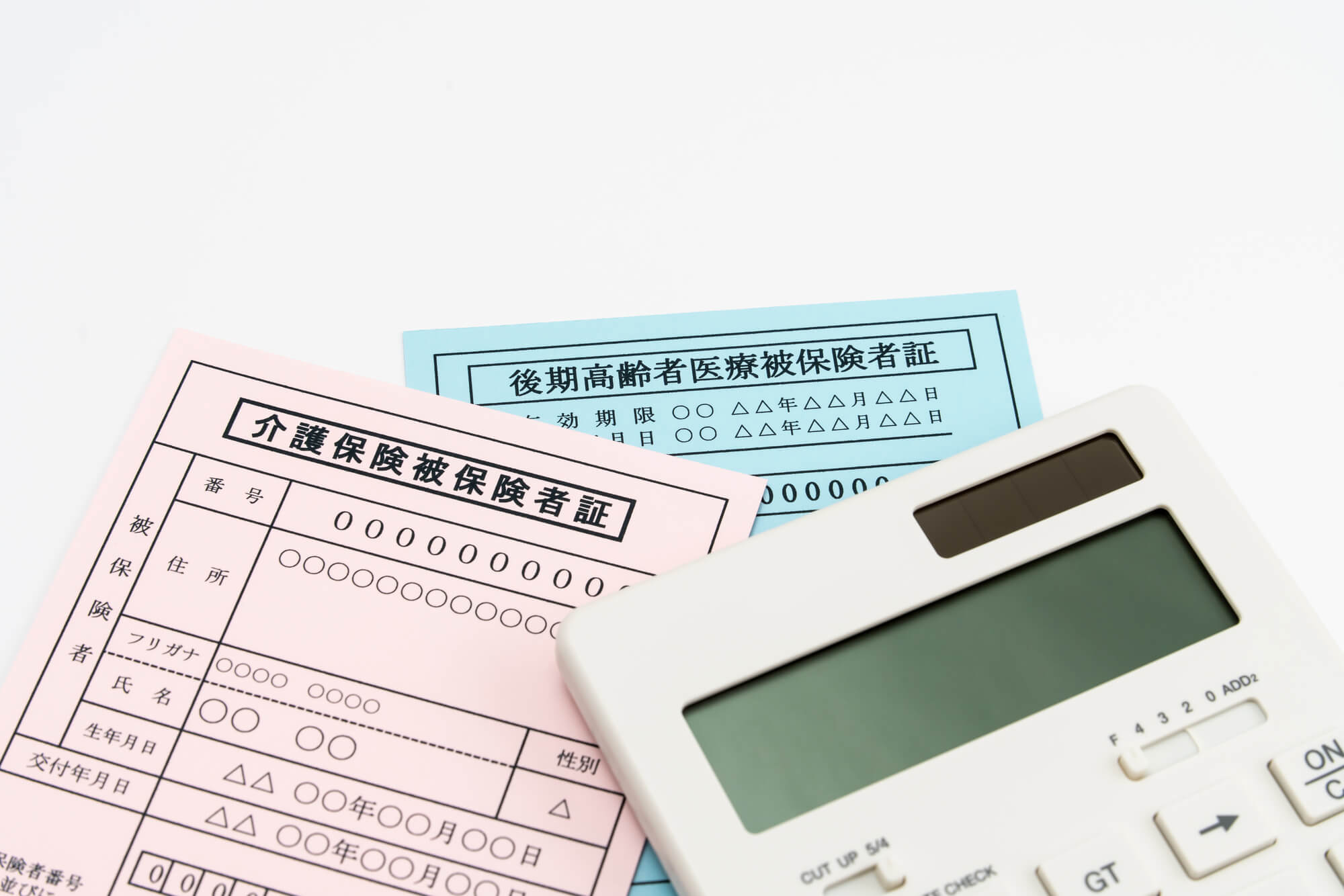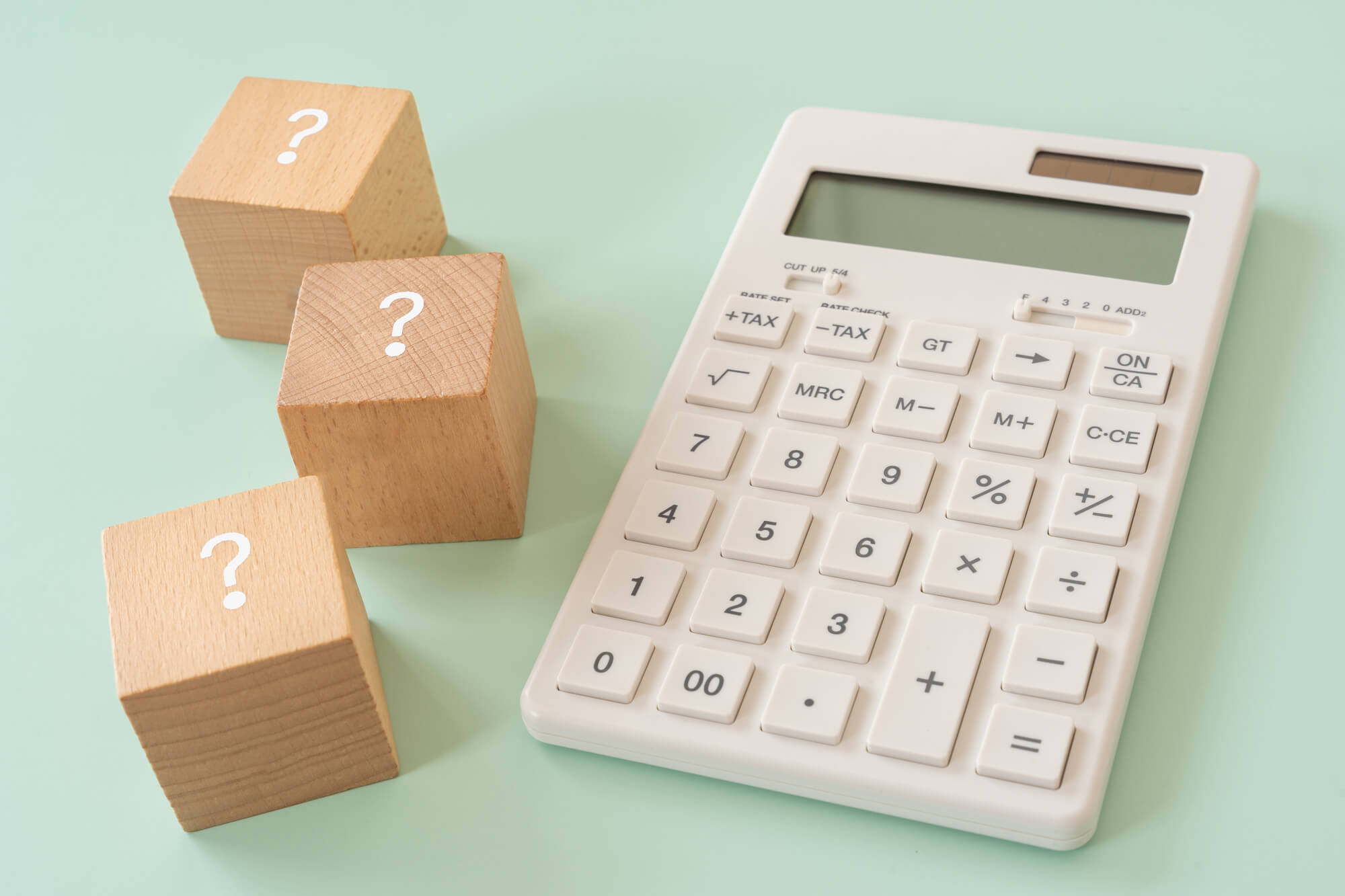介護保険料はいくらになる?計算方法や支払い方法などを解説

介護保険料を支払っている方やこれから支払う方の中には、一体どのくらいの負担なのか気になっている方もいるのではないでしょうか。
介護保険料は、一定の要件を満たした場合に必ず支払わなくてはならないため、具体的にいくら納める必要があるのか把握しておくことが大切です。
この記事では、介護保険料の計算方法・支払い方法・知っておくべきことについて解説します。介護保険料の計算方法について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
介護保険料の計算方法
介護保険料は、介護保険の被保険者が第1号被保険者なのか、第2号被保険者なのかで計算方法が異なります。
それぞれの介護保険料の計算方法について、詳しく見ていきましょう。
第1号被保険者
第1号被保険者とは、65歳以上の方です。介護保険料は、被保険者の住む市区町村ごとに決定されます。その理由は、市区町村ごとに介護保険を利用する方の割合や、介護サービスの提供にかかる総費用が異なるためです。
第1号被保険者の介護保険料は、前年度の所得に基づいて算出されます。また、金額は3年ごとに見直しが実施されます。本人や世帯の所得で段階的に設定されているため、所得が多いほど保険料が高くなる仕組みです。
この段階は、各市区町村が条例で決めることができるため、何段階に設定されているかは各市区町村で異なります。そのため、詳しくは市区町村の窓口で確認することをおすすめします。
なお、厚生労働省が公表しているデータによると、令和3~5年度の第1号被保険者の介護保険料の平均額は6,014円という結果でした。
参照:厚生労働省「令和5年度 介護納付金の算定について」
第2号被保険者
第2号被保険者とは、40~64歳までの公的医療保険に加入している方です。介護保険料は、それぞれの医療保険制度によって違います。
会社の健康保険に加入している方の場合、標準報酬月額に基づき介護保険料が決まります。標準報酬月額とは、毎年4~6月の給与の平均額を標準報酬月額表に記載されている等級に当てはめて決定するものです。
標準報酬月額表は、都道府県および自分の会社が加入する健康保険組合によって変化します。会社員の場合は、被保険者と事業者で介護保険料を折半し、夫や妻の扶養に入っている方は保険料を納める必要はありません。
国民健康保険に加入する自営業者やフリーランスの方の場合、所得や世帯の被保険者の人数、資産などによって市区町村が決めた介護保険料を納めることになります。
なお、令和5年度の第2号被保険者の介護保険料の見込み額は6,216円という結果でした。
参照:厚生労働省「令和5年度 介護納付金の算定について」
介護保険料の支払い方法
介護保険料の支払い方法も、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。
それぞれの支払い方法について詳しく解説します。
第1号被保険者
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、基本的に年金から天引きされる仕組み(特別徴収)となっています。年間18万円以上の年金を受け取っている方は、特別徴収となるため自身で行う手続きは必要ありません。
年金が年間18万円未満または年金の繰り下げ受給を選んだ方は、普通徴収となります。市区町村から送付される納付書や口座振替によって、介護保険料を納付します。
介護保険料を専業主婦(主夫)として配偶者の健康保険料とともに納付してきた方も、65歳を迎えると特別徴収または普通徴収のいずれかの方法で納付が必要です。
第2号被保険者
第2号被保険者(40~64歳までの方)の介護保険料は、医療保険料とともに徴収されます。会社員の場合、介護保険料は医療保険料に上乗せされ、給与から天引きされる仕組みです。
給与から天引きされる場合、被保険者は自身で支払いを行う必要はなく、雇用主が毎月の給与から保険料を差し引いて納付してくれます。
一方、自営業者やフリーランスなどの国民健康保険の加入者は、口座振替や納付書を役所・銀行・コンビニなどに持参して支払います。給与天引きとは異なり、自身で介護保険料を納付しなくてはならないため、支払い忘れに注意が必要です。
介護保険料で知っておくべきこと
介護保険料は、仕組みを正しく理解しておかないとトラブルに発展する可能性があります。トラブルを未然に防ぐためにも、以下の注意点を知っておくことが重要です。
- ・介護保険料を滞納した場合のペナルティ
- ・介護保険料が減免・猶予されるケース
- ・65歳以上は負担が大きくなる可能性がある
それぞれの注意点について詳しく説明します。
介護保険料を滞納した場合のペナルティ
介護保険料を滞納した場合、滞納期間に応じてペナルティを受けることになります。例えば、滞納期間が1年未満の場合は、納付期限から20日以内に督促状が発行されます。延滞金や督促手数料などが請求され、通常よりも多くの支出を伴うことになるため注意が必要です。
滞納期間が1年以上の場合は、通常1~3割負担で利用できる介護サービスを全額自己負担する必要があります。ただし、滞納分を納付して申請することで、本来の自己負担の金額を超えて支払った分は償還してもらえます。
1年半以上になると、滞納分を納付して申請したとしても、本来の自己負担の金額を超えて支払った分が償還されることはありません。2年以上が経過すると、滞納していた介護保険料を後から納付できなくなり、自己負担の割合が3~4割へと引き上げられ、高額介護サービス費制度を利用できなくなるため注意が必要です。
介護保険料が減免・猶予されるケース
介護保険料を滞納しなければ、ペナルティを受けることはありません。しかし、著しい収入の減少や自然災害の影響による支出の増加など、予期せぬことが原因で介護保険料の支払いが困難になる可能性もあります。
このような場合は、介護保険料の減免を申請することができます。申請が認められると、3カ月程度~1年まで保険料が減免されるほか、納付期限を延長してもらえます。
例えば、長期の入院や事業の廃止、失業などで収入が減少する可能性がある場合は、前もって市区町村に申請すると、ペナルティを回避できるだけでなく、減免や納付期限延長の措置を取ってもらえることもあります。
65歳以上は負担が大きくなる可能性がある
65歳を迎えて第1号被保険者になると、介護保険料の負担が大きくなる可能性があるため注意してください。
その理由は、介護保険料の計算方法が第1号被保険者と第2号被保険者で異なることと、会社員の介護保険料が勤務先との折半から全額自己負担へと変わるためです。
第1号被保険者の介護保険料は本人の所得だけでなく、その地域に住んでいる65歳以上の方の人数や、介護サービスにかかる費用の見込み額などを踏まえて決まります。そのため、自治体によっては負担金額が大きくなる可能性があります。
また、会社員は64歳まで介護保険料を会社と折半し、会社が負担した残りの半分が自己負担でした。しかし、65歳を迎えると会社の負担分がなくなり、自己負担金額が大きくなるため覚えておきましょう。
まとめ
介護保険料は、40歳を迎えると支払い義務が発生します。介護保険料の計算方法は、被保険者が第1号被保険者なのか、第2号被保険者なのかによって異なります。
介護保険料が給与や年金から天引きされる場合は問題ありませんが、自身で支払う必要がある場合には、支払いを忘れることがないように注意が必要です。
また、第2号被保険者から第1号被保険者に変わる際は、介護保険料の計算方法が変わり、自己負担分が全額になることで負担金額が大きくなる可能性があります。介護保険料の知識不足が原因でトラブルに発展しないよう、正しい知識を身に付けましょう。
加齢に伴い生活に不安を抱くようになった場合には、シニア向け賃貸住宅も選択肢の一つです。
ヘーベルVillageは、シニア向け安心賃貸住宅を提供しています。シニア向け安心賃貸住宅は、駆けつけサービス・健康や暮らしをサポートする相談サービス・看護師による健康相談・医療機関の紹介サービスなど、さまざまなサポートが充実しています。
自立しながら安心して老後を暮らしたいという方は、ぜひ旭化成ホームズのヘーベルVillageにご相談ください。