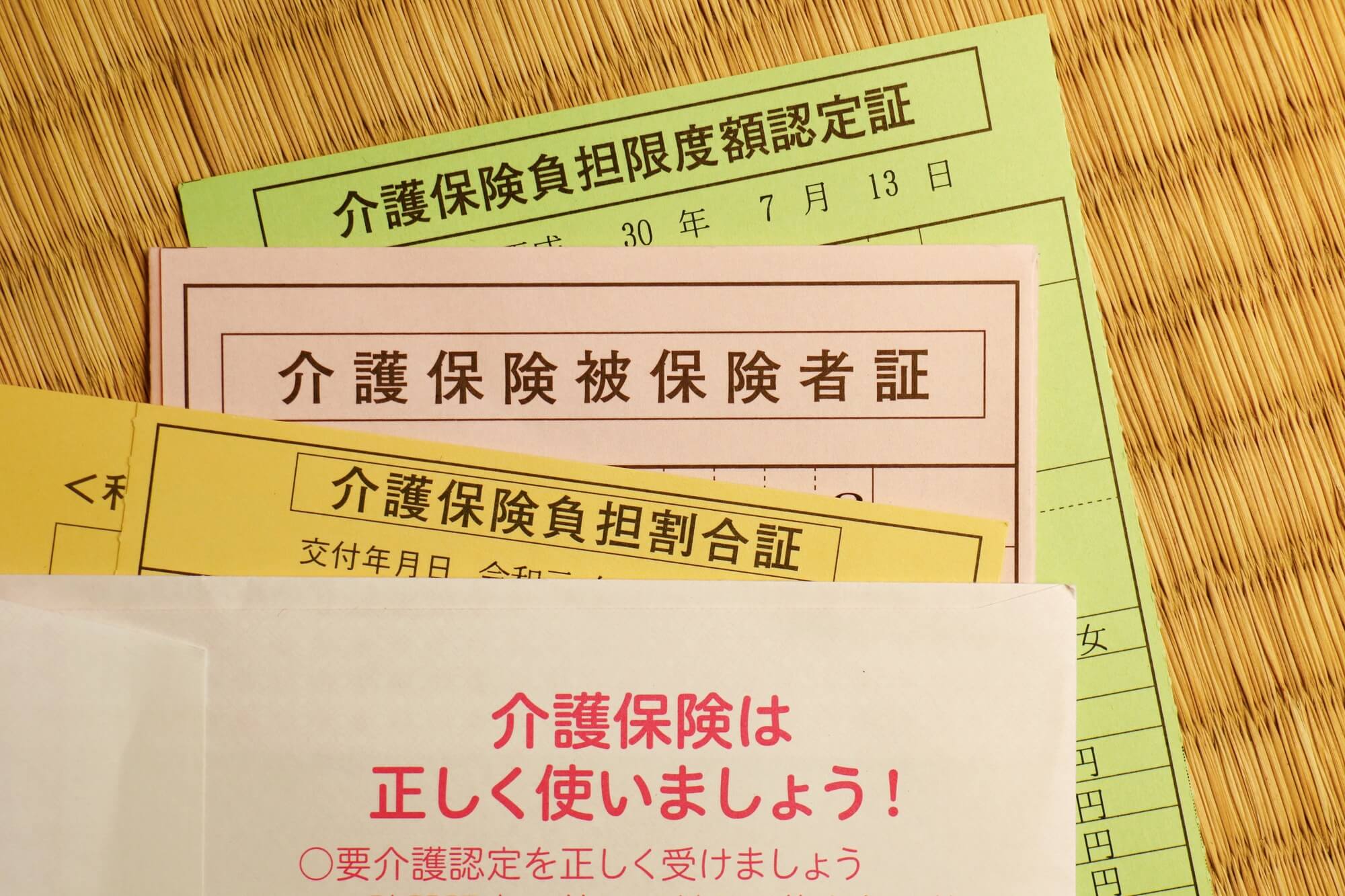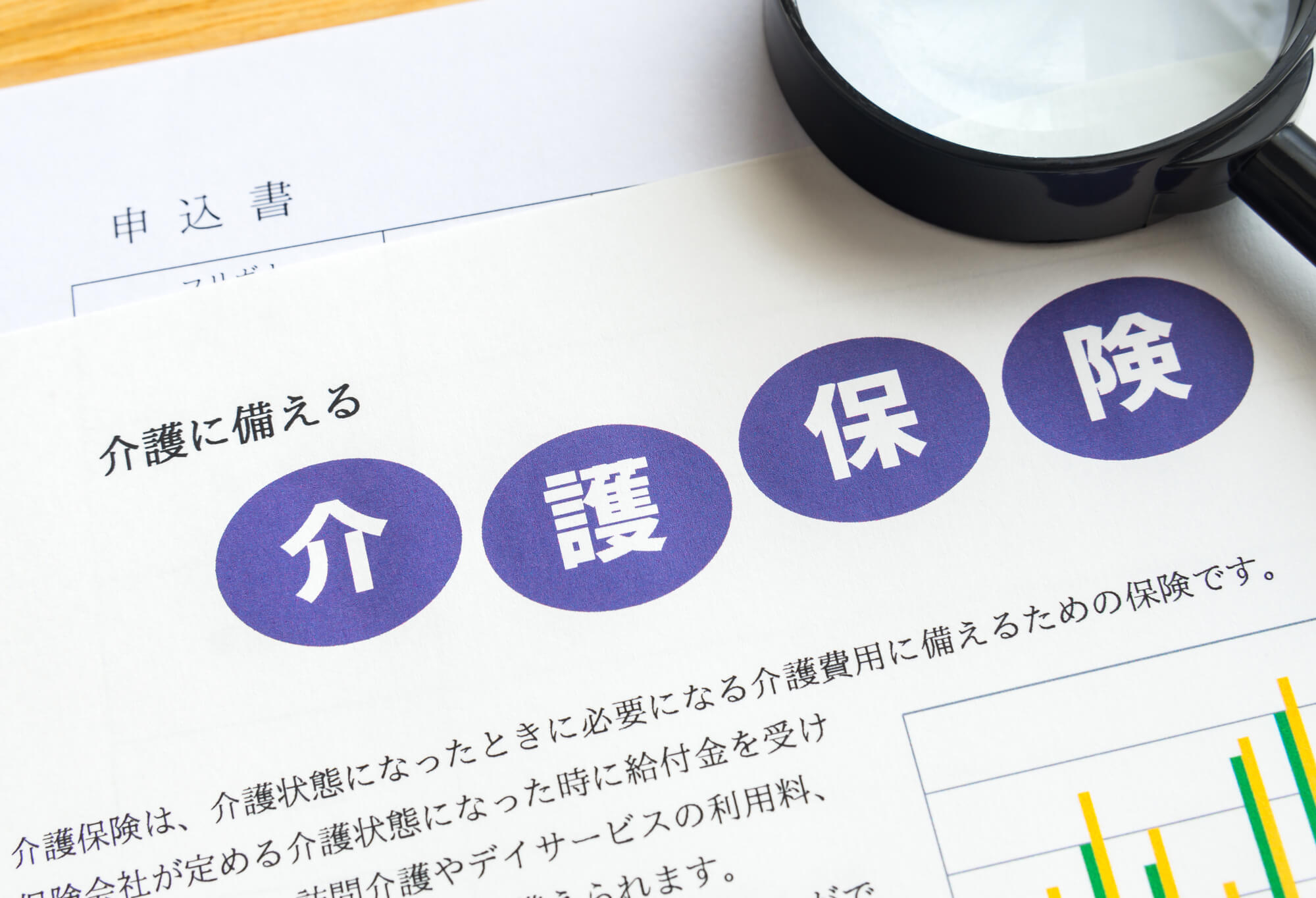65歳以上の介護保険料の負担はどうなる?納付額や納付方法などを紹介

介護保険料は、一定の要件を満たす方が納める社会保険料のことで、介護サービスを提供する財源確保のために使用されます。
65歳になると、介護保険における区分が第1号被保険者となるため、介護保険料の負担が大きくなってしまわないか不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、介護保険料とは何か、65歳以上における介護保険料の注意点、65歳以上の介護保険のポイントなどを解説します。介護保険料の仕組みについて詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
介護保険料とは
介護保険とは、日本における公的な社会保険制度で、高齢者などが必要としている介護サービスを提供するためのものです。
介護が必要な方が少ない自己負担で介護サービスを利用できるように、社会全体で介護を支えるために徴収されているのが介護保険料なのです。
介護保険料は、一定の要件を満たす方のみが負担します。介護保険料の支払いについて詳しく見ていきましょう。
40歳から支払い義務が発生する
介護保険料の支払い対象者は、介護保険制度の第1号被保険者および第2号被保険者です。第1号被保険者と第2号被保険者の違いは、以下の通りです。
- ・ 第1号被保険者:65歳以上
- ・ 第2号被保険者:40~64歳の医療保険加入者
介護保険制度の加入義務があるのは40歳以上の方で、40歳から介護保険料の支払い義務が発生するということを意味します。
65歳以上になっても支払いは続く
国民年金は基本的に20~60歳までの40年間、厚生年金は雇用されている間(退職または、企業に勤めていて70歳を迎えるまで)に保険料を支払います。保険料納付期間の経過後は、保険料を納める必要はなく年金を受け取ることが可能です。
一方、介護保険制度の介護保険料は、何歳までという概念がありません。第1号被保険者に切り替わった65歳以降についても保険料を納付しなくてはならず、介護保険料の支払いは一生涯続くということを覚えておきましょう。
65歳以上における介護保険料の注意点
65歳以上の第1号被保険者は、40~64歳までの第2号被保険者と異なる点が複数あります。この違いが原因で何らかのトラブルに発展する可能性があるため、注意すべき点を知っておくことが必要です。65歳以上の介護保険料の注意点として、以下の2つが挙げられます。
- ・ 納付方法が天引きではなくなる
- ・ 負担が大きくなる可能性がある
それぞれの注意点を詳しく解説します。
納付方法が天引きではなくなる
40~64歳までの第2号被保険者で会社員の場合は、健康保険料と併せて介護保険料を給与から天引きする形で納付します。自営業といったように国民健康保険に加入している方も、国民健康保険料と併せて徴収されます。
65歳以上の第1号被保険者は、単に区分が変わるだけでなく、納付方法が変更になるので注意が必要です。65歳を迎えた後も会社員として働き続けている方であっても、この変更は同様です。
65歳以上の納付方法について詳しくは後述しますが、40~64歳までとは違うということを覚えておきましょう。
負担が大きくなる可能性がある
介護保険料の算出方法は、40~64歳までの第2号被保険者と65歳以上の第1号被保険者で異なります。算出方法の詳細は後述しますが、第1号被保険者の場合は、地域差による影響が大きくなります。そのため高齢者の割合が大きい地域では、介護サービスの需要が高く、それに応じて保険料が高く設定される可能性があるので注意が必要です。
また、会社員の場合は、64歳までは介護保険料を会社と従業員で折半します。そのため、64歳までは実際の負担額の半分で済むのです。しかし65歳以上となると、会社の負担分が自己負担へと変わることで、負担額が大きくなる点に注意してください。
65歳以上の介護保険のポイント
第1号被保険者となる65歳以上は、第2号被保険者とは異なる点が増えます。トラブルを回避するためにも、以下の4つのポイントを把握しておくことが大切です。
- ・ 介護保険料の平均負担額
- ・ 介護保険料の納付方法
- ・ 介護保険料の滞納した場合のペナルティ
- ・ 介護保険料の納付が免除されるケース
それぞれのポイントについて詳しく説明します。
介護保険料の平均負担額
厚生労働省が公表している「令和5年度 介護給付金の算定について(報告)」によると、令和3~5年度の第1号保険料の平均額(月額)は6,014円、令和5年度の第2号保険料の見込額(月額)は6,216円という結果でした。
第2号保険料は毎年見直されますが、第1号保険料の金額は3年ごとに見直されています。第1号・第2号保険料共に年々上昇しており、負担が大きくなっているので注意が必要です。
参照:厚生労働省「令和5年度 介護給付金の算定について(報告)」
介護保険料の計算方法
介護保険料は年々負担額が大きくなっていますが、保険料は明確な根拠に基づいて算出されています。例えば、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、各自治体で設定された基準額に加え、本人や世帯の所得状況によって変化します。
基準額とは、介護サービスに必要な費用および第1号被保険者が負担する割合を、自治体に居住する65歳以上の人数で割った金額です。
第1号被保険者は、9段階や16段階といったように所得状況で段階別に区分されています。例えば新宿区では、第1段階が年額で19,800円、第18段階は459,350円といったように段階ごとに保険料が異なります。
参照:新宿区「介護保険料の決まり方」
また、40~64歳までの第2号被保険者は、国民健康保険者の場合は「介護保険料=所得割額+均等割額+平等割額+資産割額」国民健康保険以外の医療保険加入者の場合は「介護保険料=標準報酬月額(または標準賞与額)×介護保険料率」で算出します。なお、協会けんぽの保険料率は、令和6年3月分(4月30日納付期限分)からの分で1.60%となっています。
参照:全国健康保険協会「協会けんぽの介護保険料率について」
介護保険料の納付方法
65歳以上の第1号被保険者の介護保険料の支払い方法は、以下のいずれかです。
- ・ 特別徴収
- ・ 普通徴収
年金受給額が1年間で18万円以上の場合は、特別徴収が適用され、年金から自動的に介護保険料から差し引かれます。特別な手続きは必要ありませんが、自動で天引きされるまでに半年~1年程度の準備期間が必要で、準備が整うまでは納付書や口座振替で納付しなくてはなりません。
一方、18万円未満の場合は普通徴収となるため、納付書や口座振替で納付します。納付書の場合は、役所や銀行、コンビニなどで保険料を支払います。
介護保険料を滞納した場合のペナルティ
特別な事情がないにもかかわらず保険料を滞納した場合は、滞納した期間に応じて以下のペナルティを受けることになるので注意してください。
- ・ 納付期限を過ぎてから1年未満:お住いの自治体から納付の督促
- ・ 1年以上の滞納:介護サービス費用を一旦全額自己負担
- ・ 1年6か月以上の滞納:保険給付が一時差し止め、その中から滞納している分を徴収
- ・ 2年以上の滞納:滞納期間に応じてサービス費用の利用者負担の割合が引き上げ
滞納した期間に応じて保険給付を制限する措置がとられるため、忘れずに納付しましょう。
参照:品川区「介護保険の対象と保険料」
介護保険料の納付が免除されるケース
40歳を迎えると介護保険料の納付義務が発生しますが、生活保護を受けている方は納付が免除されます。
生活保護を受けている方は、医療保険に加入できません。よって、公的介護保険の被保険者とならず、介護保険料の負担がなくなります。65歳以上の生活保護受給者の方の介護保険料は、生活保護における生活扶助費でまかなわれるため、実質的な自己負担はありません。
他にも、地震や火災などの災害で大きな損害を受けた場合は、介護保険料を減免・猶予してもらえる可能性があります。介護保険料の納付が困難な方は、どのようなケースで減免・免除されるのか確認してみましょう。
まとめ
介護保険は、40歳を迎えると加入が必須で、基本的に介護保険料を納めなくてはなりません。介護保険料の支払いは、原則一生涯であるため65歳以上になっても介護保険料の支払いが続くことになります。
滞納した場合は、何らかのペナルティを受けることになるため忘れずに納付しましょう。
まだ介護サービスを受ける必要はないものの、加齢に伴い生活に不安を抱いている方には、シニア向け賃貸住宅がおすすめです。
ヘーベルVillageは、シニア向けの安心賃貸住宅を提供しています。駆けつけサービス・健康や暮らしをサポートする相談サービス・看護師による健康相談・医療機関の紹介サービスなど、さまざまなサポートが充実しています。
自立しながら安心して老後を暮らしたいという方は、旭化成ホームズのヘーベルVillageにご相談ください。