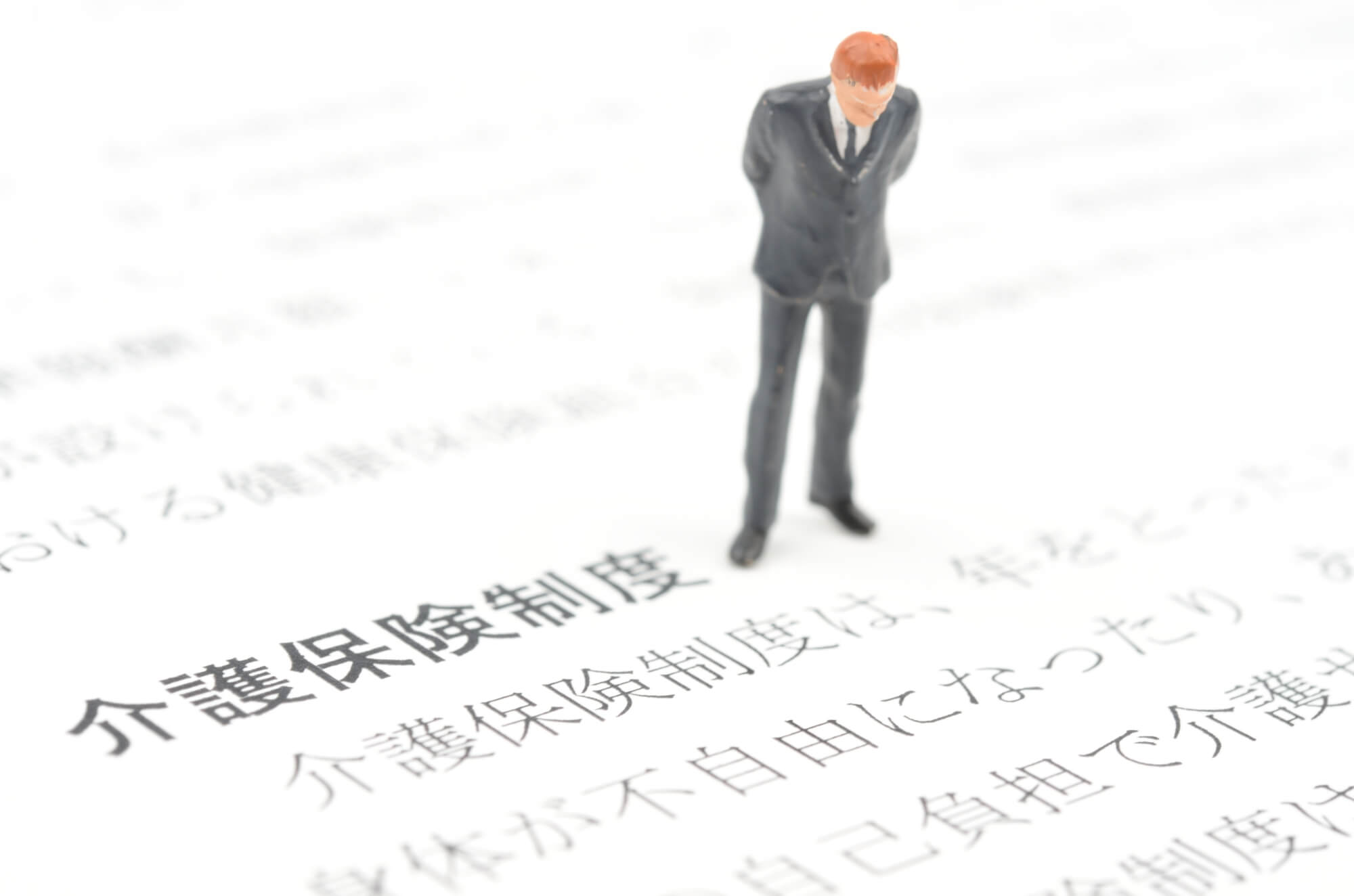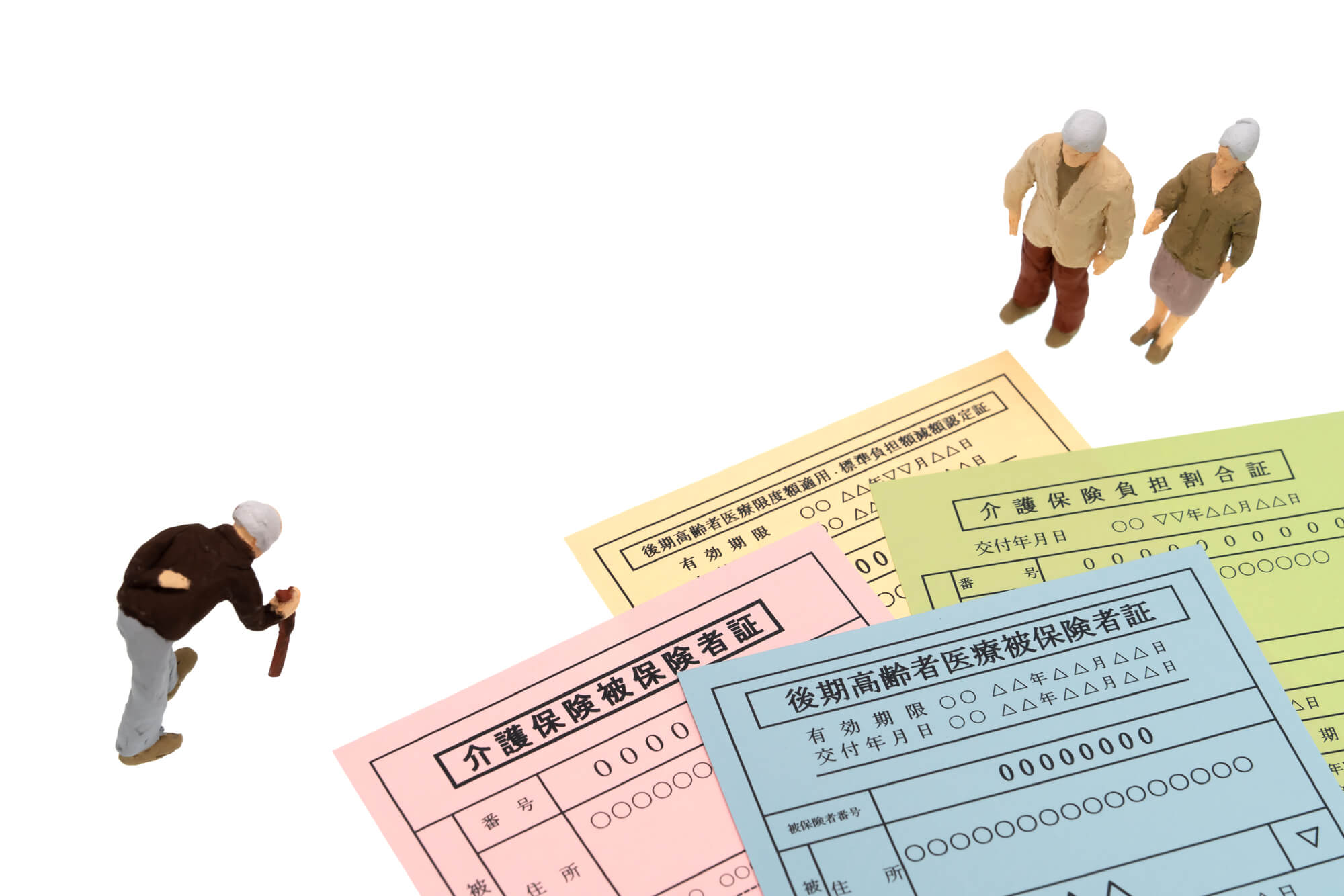介護保険サービスってどんなもの?在宅介護の介護保険サービスを紹介
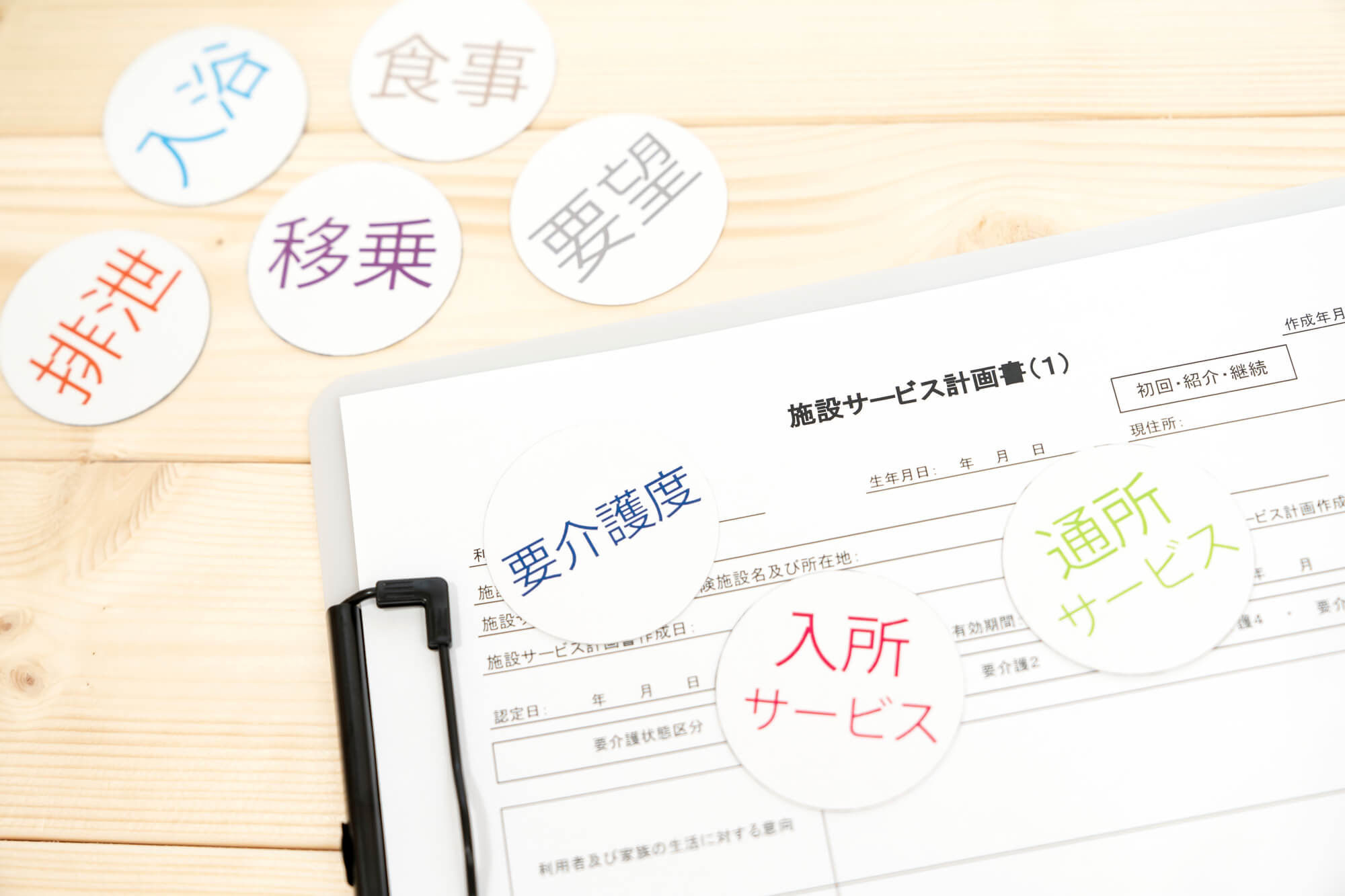
在宅での介護保険サービスの利用を検討している方の中には、どのような介護サービスを利用できるか気になっている方も多いのではないでしょうか。
訪問型や通所型など、介護保険サービスの種類は多く、自身の状況に合ったサービスを選択することが大切です。
この記事では、訪問型と通所型の介護保険サービスの詳細や、訪問型と通所型を複合させた介護保険サービスについてなどを解説します。介護保険サービスについて詳しく知りたい方は、是非参考にしてください。

介護保険サービスの利用手続きとケアプランの作成方法
介護保険サービスを利用するには、一定の手続きを踏まなくてはなりません。まず要介護認定を受け、その結果に基づいてケアプラン(介護サービス計画)を作成して初めてサービスの利用が可能となります。
制度は一見複雑に思えるかもしれませんが、自治体や地域包括支援センターなどの支援を受けながら進めることで、負担を軽減できます。
この章では、申請からサービス利用開始までの流れ、ケアプラン作成の重要なポイントを解説します。
介護保険サービスを利用するための流れ
介護保険サービスを利用するには、まずは市区町村の介護保険窓口で要介護認定の申請を行います。申請後、調査員による認定調査が行われて、主治医の意見書と合わせて審査が進められます。認定結果が通知された後、介護支援専門員(ケアマネジャー)との面談を通じてケアプランを作成します。
そのプランに基づいて、介護サービスの提供が開始されるという流れです。地域包括支援センターなどの支援機関を利用することにより、手続きを円滑に進めることができます。申請から利用開始までの一連の手続きには時間がかかるため、早めの行動が大切です。
要介護認定の申請方法
要介護認定の申請は、原則として本人または家族が行い、市区町村の介護保険担当窓口で受け付けられます。申請時には、健康保険証や介護保険被保険者証が必要です。申請後は、認定調査員が本人の生活状況や身体の状態を調査して、主治医の診断書とともに介護認定審査会で判定されます。
認定結果は「非該当」から「要支援1~2」「要介護1~5」の7区分に分類され、通常は申請から約30日以内に通知されます。結果に対して不服がある場合、再審査の申し立ても可能です。必要書類や手続きに不安があるという方は、地域包括支援センターでの相談がおすすめです。
介護保険で利用できるサービスは要介護度によって違い、要介護1~5の方は介護給付、要支援1~2の方は予防給付というサービスを利用できます。
参照:厚生労働省「公表されている介護サービスについて」
ケアプランとは?作成の流れとポイント
ケアプランは、要介護認定の結果に基づき、利用者の希望または生活状況などに合わせて作成される介護サービスの利用計画書です。作成は原則、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーが行います。
初回は面談を通じて生活課題や目標などを明確にし、それらに基づいて適切なサービスが組み合わされます。ケアプランは柔軟に見直すことが可能で、定期的に評価されるため、生活の変化に応じた支援を受けることが可能ですが、利用者と家族の意向が十分に反映されるように、丁寧な対話が重要です。それにより、利用中の悩みや不安も随時相談でき、安心して在宅介護を継続することが可能となります。
訪問型の介護保険サービスとは

介護保険サービスとは、介護保険の対象となるサービスのことです。要介護になったものの、在宅での介護サービスの利用を希望している方も多いのではないでしょうか。
在宅で利用できる介護保険サービスは、訪問型と通所型に分類されます。訪問型の介護保険サービスには、以下のように多くの種類があります。
- ・訪問介護
- ・訪問入浴介護
- ・訪問看護
- ・訪問リハビリテーション
- ・居宅療養管理指導
- ・夜間対応型訪問介護
- ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
それぞれの違いについて詳しく見ていきましょう。
訪問介護
訪問介護とは、利用者がなるべく自立した生活を送ることができるようにサポートをする介護保険サービスです。
訪問介護員が利用者の自宅を訪問して、食事や排せつ、入浴などの身体介護、掃除や洗濯、買い物、調理などの生活支援を行います。
訪問入浴介護
訪問入浴介護とは、入浴介護に特化した介護保険サービスです。利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を目的としており、生活機能の維持または向上を目指しています。
看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問して、持参した浴槽で入浴の介助をします。
訪問看護
訪問看護とは、疾患のある利用者を対象とする介護保険サービスです。利用者の心身機能の維持・回復を目的としています。
看護師などが利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に従って療養上の世話や診療の補助を行いつつ、利用者がなるべく自立した生活を送ることができるようにサポートします。
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションでは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問します。
利用者がなるべく自立した生活を送ることができるように、各専門家によって心身機能の維持回復、日常生活の自立に向けたリハビリなどが行われます。
居宅療養管理指導
居宅療養管理指導とは、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などの専門家が自宅を訪問します。
通院が困難な利用者の自宅を訪問し、心身の状況や置かれている環境などを踏まえながら療養上の管理や指導を行い、利用者の療養生活の質の向上を図ります。
夜間対応型訪問介護
夜間対応型訪問介護では、訪問介護員が夜間に利用者の自宅を訪問します。
定期的に訪問介護員が訪問してくれる定期巡回と必要に応じてサービスを受けられる随時対応の2つがあり、利用者がなるべく自立した生活を送れるように日中だけでなく夜間もサポートします。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、利用者が日々の生活を可能な限り自立して過ごせるように、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供します。
定期的な巡回やトラブル発生時の通報への対応など、それぞれの状況に合わせて自立した生活を送ることができるようなサポートが受けられます。
訪問介護員のほか、看護師とも連携しているため、介護と看護の両方のサポートが可能です。

通所型の介護保険サービスとは

必要なサービスを施設に通うことで受けられる通所型の介護保険サービスとして、以下の種類が挙げられます。
- ・通所介護(デイサービス)
- ・通所リハビリ(デイケア)
- ・短期入居生活(療養)介護(ショートステイ)
それぞれの違いを詳しく解説していきます。
通所介護(デイサービス)
通所介護とは、自宅にこもりきりになっている利用者の孤独感の解消、家族の介護の負担軽減や心身機能の維持といった目的で実施される介護保険サービスです。
通所施設や、利用定員が19人以上のデイサービスセンターなどに通所して、食事や入浴などの日常生活の支援、生活機能の向上を目的とした機能訓練のほか、口腔機能向上サービスなどが受けられます。
また、高齢者同士の交流を通じて生活機能の向上も期待できます。
通所リハビリ(デイケア)
通所リハビリでは、老人保健施設や病院、診療所などのリハビリ施設に通って介護保険サービスを受けることができます。
食事や入浴などの日常生活の支援、生活機能の向上を目的とした機能訓練のほか、口腔機能向上サービスなどが受けられるのが特徴です。
介護予防通所リハビリでは、生活機能の向上を目的とした共通的サービスに加えて、個々の利用者の心身の状況に合わせて運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上などのサービスを組み合わせて受けることもできます。
短期入居生活(療養)介護(ショートステイ)
短期入居生活介護(ショートステイ)とは、特別養護老人ホームといった介護老人福祉施設が常に介護を必要とする方の、短期間の入所を受け入れる介護保険サービスです。
一方、短期入所療養介護とは、介護老人保健施設・介護医療院・医療機関が介護サービスを行うものです。
どちらも自宅にこもりきりの利用者の孤独感の解消、家族の介護の負担軽減や心身機能の維持などを目的としています。
入浴や食事などの日常生活上の支援、機能訓練といった介護保険サービスを受けることが可能です。
訪問型と通所型を複合した介護保険サービスとは
自宅に居ながら介護保険サービスを利用できる訪問型、施設に通って介護保険サービスを受ける通所型を複合したものとして、以下の2つが挙げられます。
- ・小規模多機能型居宅介護
- ・看護小規模多機能型居宅介護
それぞれの違いを詳しく説明していきます。
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護とは、利用者の選択に応じ、施設への通所を中心に短期間の宿泊や利用者の自宅への訪問を組み合わせた介護保険サービスです。
家庭的な環境と地域住民との交流を通じつつ、日常生活の支援や機能訓練を受けられます。
看護小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護では、小規模多機能型居宅介護と同様、利用者の選択に応じ、施設への通所を中心に短期間の宿泊や利用者の自宅への訪問を組み合わせることが可能です。また、必要に応じて看護師による訪問も組み合わせることができます。
家庭的な環境と地域住民との交流を通じつつ、介護と看護の両方を受けられます。
福祉用具貸与・住宅改修による在宅介護の支援

在宅介護を安全・快適に行うには住環境の整備と適切な福祉用具の導入が欠かせません。介護保険制度では、福祉用具の貸与や住宅の一部改修に対して支援が受けられる仕組みが整っており、要介護者の自立支援や介護負担の軽減につながります。
ここでは、福祉用具貸与サービスと住宅改修制度の概要、具体的な内容とその活用方法、そしてそれらを組み合わせることで得られるメリットなどを解説します。
福祉用具貸与サービスとは
福祉用具貸与サービスは介護保険を活用して必要な福祉用具をレンタルできる制度です。対象となるのは、車いす、特殊寝台、手すり、歩行器といった日常生活の動作を支援する用具です。
購入ではなく貸与なので、必要な期間のみ費用を抑えて利用でき、状態の変化に応じた入れ替えにも柔軟に対応できます。要介護度に応じて給付対象となる用具が違うことから、ケアマネジャーと相談しながら適切な選定を行うことが大切です。使いやすさや安全性も考慮して選ぶことが、介護の質を高める鍵となります。
介護保険を利用した住宅改修とは
介護保険を利用した住宅改修は在宅での生活を安全に送るための住宅の一部工事に対して補助が受けられる制度です。対象の工事には、手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止床材の変更、扉やトイレの改修などがあります。
上限は20万円(自己負担は原則1割)ですが、一生に一度ではなく、要介護度が大きく変わった際などに再申請が可能です。改修には事前の申請と見積もりが必要となるため、工事を急ぐ場合でも、手続きを怠らず行うことが欠かせません。介護のしやすさだけでなく、事故防止につながる大切な支援制度です。
在宅介護における福祉用具・住宅改修のメリット
福祉用具と住宅改修を上手に活用すれば、要介護者が自立して生活できる範囲が広がり、介護者の身体的・精神的な負担も大きく軽減されます。転倒や転落などの事故の予防にも効果があり、介護の現場での不安や緊張を和らげることにもつながります。
また、介護保険の支給範囲内で賢く利用することで、経済的な負担を抑えながら質の高い在宅介護環境を整えることができます。これらを利用する際には、ケアマネジャーや福祉住環境コーディネーターと連携し、住まいおよび身体状況に合った最適なプランを立てましょう。
地域密着型サービスとその活用方法
介護が必要になったとき、住み慣れた地域で支援を受けられることは、本人にも家族にも大きな安心感をもたらします。地域密着型サービスは、各市町村が主体となって提供する介護サービスであり、地域の実情に応じた柔軟な支援が特徴です。
とくに認知症高齢者や重度の要介護者の支援に有効で、地域資源を活かしたきめ細やかなサービス提供が可能です。
ここでは、地域密着型サービスの概要や具体的な内容、選び方のポイントを紹介します。
地域密着型サービスとは?
地域密着型サービスは、利用者が住み慣れた地域で可能な限り自立した生活を送れるよう市町村単位で提供される介護保険サービスです。対象となるのは原則としてその市町村に住民票がある人に限られ、地域の特性や実情に合ったきめ細かな支援が可能です。
サービスの種類には、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、夜間対応型訪問介護、地域密着型特養などがあります。地域のつながりを重視し、利用者の尊厳や安心を守ることを目的としています。近隣の支援資源との連携も進めやすく、在宅介護を支える重要な柱といえるでしょう。
認知症対応型通所介護とグループホームの特徴
認知症対応型通所介護は認知症の高齢者が日帰りで介護サービスを受けられる施設です。専門スタッフによる見守りや機能訓練、レクリエーションなどが行われ、認知症の進行を緩やかにしながら生活の質を保つ支援が特徴です。
一方で、認知症グループホームは、認知症の方が少人数で共同生活を送りながら、職員の支援を受ける入所型のサービスです。家庭的な雰囲気の中で、食事や入浴、排泄といった日常生活を支援し、心身の安定を図ります。どちらも認知症に特化した環境が整っていて本人と家族の双方に安心感をもたらします。
地域に合った介護サービスを選ぶポイント
介護サービスを選択する際には、本人の身体状況や希望に加えて、その地域で利用できるサービス内容をよく把握することが不可欠です。地域密着型サービスは市区町村によって提供内容が違うため、まず地域包括支援センターで相談し、情報を得るのが第一歩です。
また、通いやすさ、スタッフの対応、他利用者との相性なども選定基準に含めましょう。見学や体験利用を通じて、実際の雰囲気を感じ取ることも欠かせません。地域に根差したサービスを活用することで、より安心で継続的な在宅介護が実現できます。
東京都の介護サービスについては以下のリンクから情報を入手できます。
参照:東京都「東京都介護サービス情報」
まとめ
在宅での介護保険サービスには、訪問型と通所型の2種類がありますが、両方を組み合わせた介護保険サービスもあります。
多種多様なので、自身の状況や目的に合った介護サービスを選択するためにも、それぞれの違いをしっかり理解することが大切です。
老後の生活に不安を抱いてきたものの、自立した生活を送りたいという方には、高齢者向け賃貸住宅も選択肢の1つです。
高齢者向け賃貸住宅はバリアフリーに対応、見守りサービスなどのように安心して老後を暮らせる設備や環境が整っているので、一度検討してみてはいかがでしょうか。
ヘーベルVillage(ヴィレッジ)はシニア向け安心賃貸住宅を提供しています。駆けつけサービス、健康や暮らしをサポートする相談サービス、看護師による健康相談、医療機関の紹介サービスなどサポートが充実しています。
旭化成ホームズのヘーベルVillage(ヴィレッジ)について詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。
有料老人ホームは民間が運営し、要介護1や要支援、自立の方でも入居可能な施設も多くあります。ヘーベルVillageも要介護2までの自立した方の入居が可能です。入居までのスピードが早く、サービスの自由度や設備の充実度が高く、施設の雰囲気や支援体制も多種多様であるため、家族構成や本人の希望・生活スタイルやニーズに応じた選択が可能です。詳しくは下記記事も参照してください。
→ 介護保険は何歳から?保険料支払い、サービスを利用できる年齢を解説
→ 介護保険料はいくらになる?計算方法や支払い方法などを解説
→ 介護保険を申請できる人は誰?条件や手続きの流れなどを解説