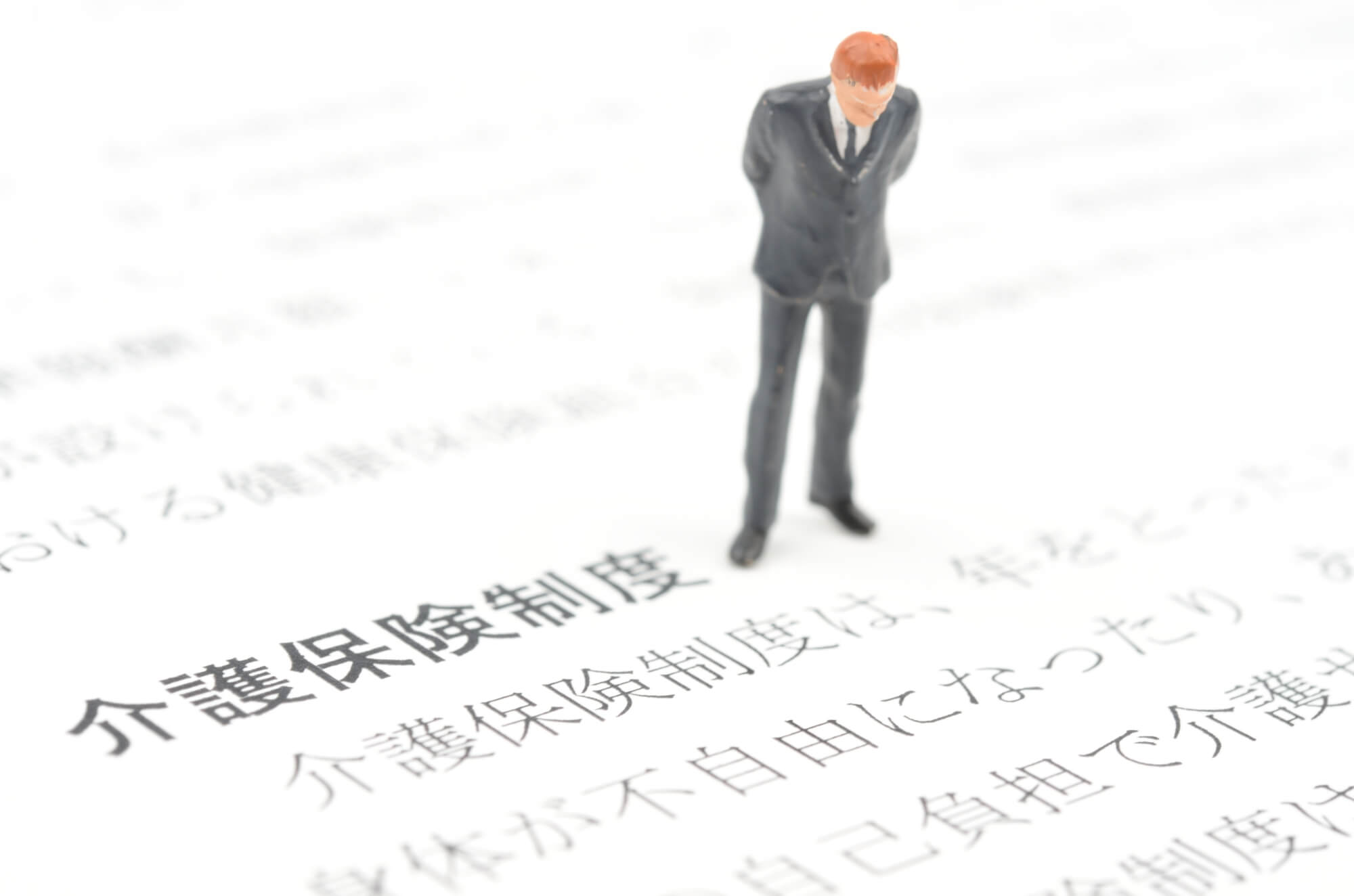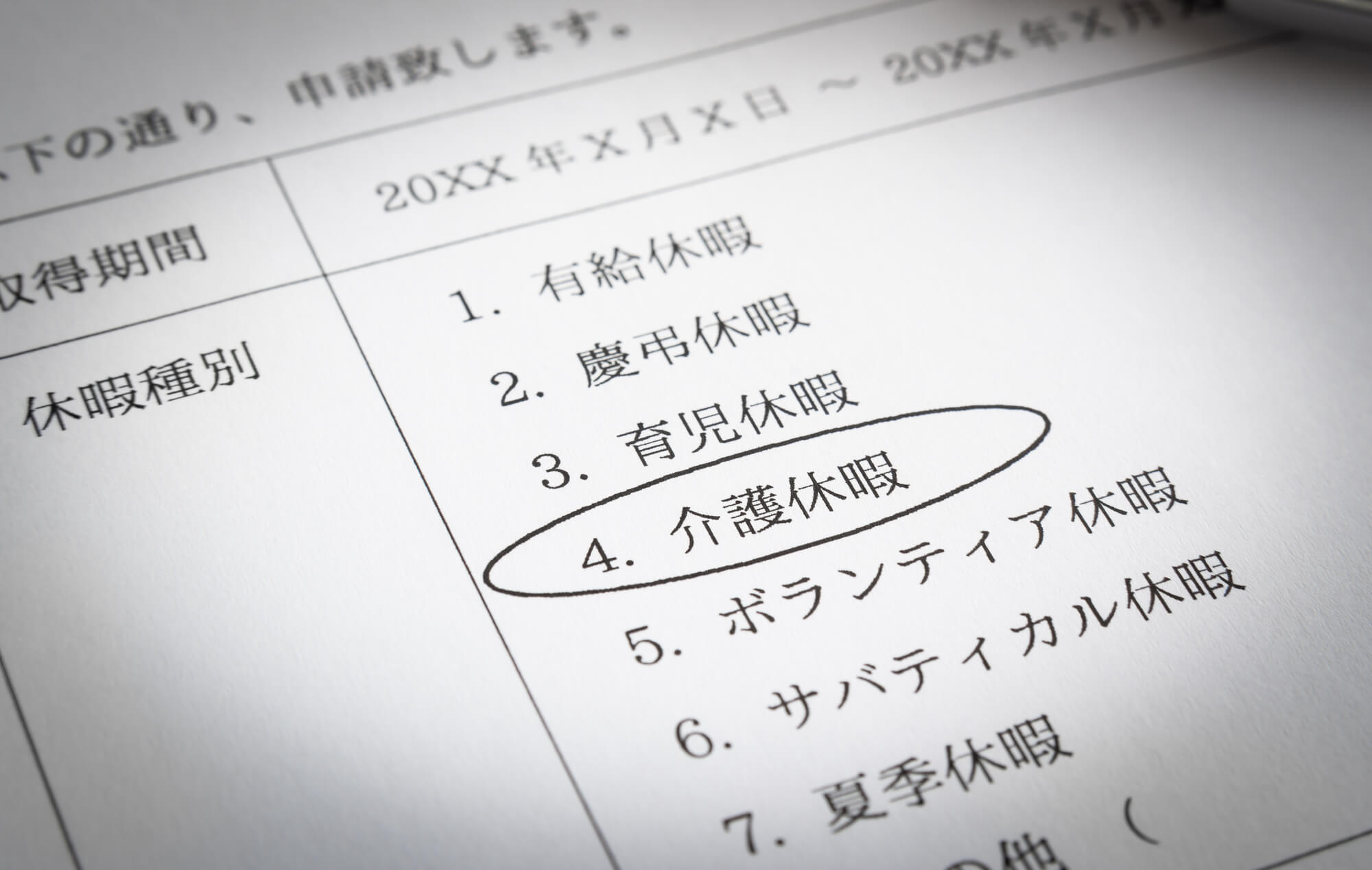高齢者の見守りサービス|種類やメリット・デメリットなどを解説

高齢者が安心して生活を送るためには、さまざまなサービスを必要に応じて活用することをおすすめします。特に見守りサービスは、万が一の際に命にも関わることなので、積極的に利用を検討したいサービスです。
そこで今回は、高齢者の見守りサービスの種類と、それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。
高齢者の見守りサービスの種類
高齢者見守りサービスの種類と特徴をご紹介いたします。
訪問型
エリアを定期的に巡回するスタッフが高齢者の自宅を訪問し、本人の様子や身の回りの心配事、体調などを質問した内容をまとめ、ご家族に報告するシステムです。安否確認と同時に、地元情報の提供や防犯の呼びかけなど、視野の広い見守りができます。
<メリット>
巡回スタッフと直接会話をするので、孤独感を減らせます。地元の郵便局員や電気・ガス会社が提供しているサービスもあるので、身元がハッキリとしており、信頼感もあるでしょう。
<デメリット>
頻繁な訪問ではないため、緊急時に対応できないのがデメリットです。また、訪問日時に在宅していなければならず、利用者によっては窮屈さを感じるかもしれません。
カメラ型
自宅に簡易カメラを設置し、日常の様子をリアルタイムで確認できる見守りサービスです。カメラの設置は大がかりな工事を必要としない上、映像はパソコンやスマートフォンで確認できます。
<メリット>
録画機能で過去の映像を見返せるだけでなく、会話機能で画面越しに話すこともできるため、高齢者の孤独感を軽減できるでしょう。リアルタイムなので緊急事態にも気付きやすく、対応の遅れを回避できます。
<デメリット>
利用者によっては常に監視されているように感じられ、ストレスになってしまう可能性もあります。
緊急時通報型
緊急時や体調不良の際に、本人が通報ボタンを押すと、スタッフが自宅に駆けつけて対応する見守りサービスです。ボタンは携帯タイプと自宅に設置するタイプがあり、いずれも電話回線やネット回線を利用します。
<メリット>
サービス提供者の管理システムは24時間対応しているため、ボタンを押せば素早く対応してもらえます。
<デメリット>
緊急時のみの利用なので、日々の様子を確認したい場合には向いていません。
センサー型
自宅設備にセンサーを取り付け、安否確認を行う見守りサービスです。家電や浴室、トイレなどを使うたびにセンサーが感知し、離れて暮らす家族のパソコンやスマホに利用情報を通知します。状況に応じて、スタッフが自宅に駆けつけることもあります。
<メリット>
生活リズムを利用するシステムのため、利用者はストレスを感じることがありません。
<デメリット>
センサーを通じて会話ができないことから、緊急時は状況を把握するまでに時間がかかります。
電話型
サービス提供者が、定期的に電話で安否確認をする見守りサービスです。電話の頻度は1日1回や週に1回など、サービス提供者によって異なり、スタッフによる食事や生活の状況、悩みなどの聞き取りを中心に行われます。
<メリット>
訪問サービスではないため、他の見守りサービスよりも金額は安く利用できます。また、サービス利用時に顔を合わせる必要がないため、家族に相談しにくい内容を話せる場合もあるでしょう。
<デメリット>
安否確認はできても、体調の細かい変化に気付くのには遅れる可能性があります。耳が悪く、人との会話が苦手な方にとっては、使いにくさを感じるかもしれません。
配食型
毎日決まった時間に、スタッフが栄養バランスの取れた食事を宅配し、安否を確認します。
<メリット>
おろそかになりがちな栄養管理のサポートが可能です。食事は、食べやすさや健康に配慮されたメニューから好きなものを選べます。
<デメリット>
食事の宅配がメインなので、緊急時にすぐ対応できません。また、配達スタッフのほとんどは高齢者の生活に関する専門知識が少ないため、総合的なサポートは難しいかもしれません。
GPS型
GPSが搭載された端末を持ち歩くことで、いつでも居場所を確認できる見守りサービスです。ただし、日常生活をサポートしてくれるタイプの見守りサービスではありません。
<メリット>
頻繁に外出することが多い方や、外出先で帰れなくなった際に心強いサービスです。
<デメリット>
端末を忘れて外出したり途中で充電が切れたりすると、家族は居場所を確認できません。また、利用者によっては行動を監視されているように感じることも考えられます。
高齢者の見守りサービスを選ぶ方法
見守り方によっては、本人にとってストレスになる場合があるため、サービスを選ぶ際には慎重さが求められます。
利用者の状況
見守りサービスの利用に抵抗を感じる方も少なくありません。利用する本人にライフスタイルを尋ねて、どの状況でどの程度の見守りが必要なのかを把握するところから始めましょう。サービスを決める際には家族の意思だけで選ばずに、本人の気持ちに寄り添うことが大切です。
費用
高齢者の見守りサービス利用料は、介護保険の適用外です。利用料金は全額自己負担なので、長期的な利用を視野に入れて、希望するサービスとサポート体制、利用頻度に見合うものを選びましょう。緊急時に利用できるオプションの料金も調べておくと、万一のときも安心です。
使いやすさ
どれだけサポートが充実していても、利用する本人が使いこなせなければ意味がありません。大きなボタンや分かりやすい表記など、使い勝手が良いものを選びましょう。あらかじめ一緒に使用方法の確認をしておけば、万一の際にすぐ使用できます。
どうしても決められない場合は専門家に相談すること
選択肢が多くて選びきれないときは、専門知識を持つ人の意見を聞くのもおすすめです。自治体の相談窓口や地域包括支援センター、ケアマネジャーなどは、高齢者の生活に関する知識も豊富なので頼りになる存在といえるでしょう。本人のライフスタイルをベースに、適切なアドバイスを提案してくれます。
なぜ見守りサービスは必要?
内閣府が発表した「令和2年版高齢社会白書」によると、2019年10月1日時点での高齢者の割合は、日本の人口全体の約30%と、1/4以上を占めています。
高齢者が事故を起こす場所の多くは、自宅内だといわれています。家族と同居をしていれば、家の中でケガや病気をしても誰かが気付いて対処してもらえますが、一人暮らしだと周りが異変に気付きにくく、対応が遅れてしまいがちです。
そこをカバーするのが高齢者見守りサービスです。遠く離れて暮らす家族に代わって高齢者の生活を手助けします。サービスによって得られるサポートは異なりますが、何かあったときに異変に気付きやすくなり、高齢者やその家族が安心して暮らしやすくなるでしょう。
高齢者の見守りサービスを選ぶポイント
高齢者の見守りサービスを選ぶ際に失敗を未然に防ぐためには、以下の8つのポイントを押さえておくことが大切です。
- ・サービスの種類と提供形態
- ・サポート体制と対応スピード
- ・利用者のニーズに合った機能かどうか
- ・費用と契約条件
- ・導入後のサポートとメンテナンス
- ・口コミと利用者の評判
- ・本人の意思をなるべく尊重する
- ・専門家に相談する
それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
サービスの種類と提供形態
高齢者の見守りサービスには、訪問型、オンライン型、遠隔監視型などと、さまざまな提供形態があります。
訪問型は介護スタッフが定期的に訪問し、直接的なサポートを提供します。オンライン型はビデオ通話やチャットなどを利用してリアルタイムでサポートし、遠隔監視型はセンサーやカメラを用いて遠方から状況を把握するのが特徴です。
各サービスにはそれぞれ特長があり、利用者の生活スタイルや健康状態に合わせて形態を選ぶことが重要です。長期的な利用を見据え、安心して続けられるサービスを選ぶためにもこれらの特徴をしっかりと理解し、最適なものを選択しましょう。
サポート体制と対応スピード
見守りサービスを選ぶ際に、サポート体制の充実度と緊急時の対応スピードは重要な選定基準です。
特に、緊急時の迅速な対応が高齢者の安全を左右します。サービス提供者が24時間体制で対応可能か、緊急時には何分以内にスタッフが現場に到着できるのかを確認しましょう。
また、家族への連絡が適切に行われるかも重要です。信頼できるサポート体制のあるサービスを選べば、利用者が安心して日常生活を送れる環境を整えることが可能になります。定期的なサポート体制の確認や、事前のリハーサルを行うことによって、いざというときの安心感を高めることができるでしょう。
利用者のニーズに合った機能かどうか
見守りサービスの選定では、利用者のニーズに適した機能が備わっていることが重要です。例えば、健康管理が求められる場合はバイタルサインをモニタリングする機能、認知症のリスクがある場合は徘徊防止機能などが求められることがあります。
その他にも、利用者の日常生活を支えるためのさまざまな機能が用意されており、これらが利用者のニーズにどれだけ適しているかをしっかりと確認する必要があります。
また、ニーズが変化した際にも柔軟に対応できるサービスを選ぶことで、長期的な安心感を得られるでしょう。機能が多岐にわたる場合、優先順位を付けて選択することが重要です。
費用と契約条件
見守りサービスの選定において、費用と契約条件は慎重に検討すべき要素です。初期費用や月額費用に加えて、オプション機能の追加料金やメンテナンス費用なども考慮しましょう。
契約期間や解約時のペナルティ、契約更新の自動延長などの有無について確認することが必要です。特に、長期的な利用を見据えて、無理のない費用設定であることが求められます。
費用対効果をしっかり検討し、サービス内容がコストに見合っているかを判断することが重要です。また、サービス利用時のトラブルを避けるためにも、契約書をしっかりと読み、分からない点は事前に確認することをおすすめします。
導入後のサポートとメンテナンス
見守りサービスを選ぶ際は、導入後のサポートとメンテナンス体制などの確認が重要です。サービスの利用中に、機器の故障やシステムの不具合が生じる可能性があるため、迅速かつ的確に対応してもらえるか、定期的なメンテナンスが含まれているかを確認しましょう。
特に、高齢者が安心してサービスを利用できるようなサポート体制が充実しているのかがポイントです。また、サービス内容のアップデートや新機能の追加への対応も考慮する必要があります。
これらの要素を十分に検討することによって、安心して長期間サービスを利用することが可能になります。サポート窓口の対応も選定時に確認しておくとよいでしょう。
口コミと利用者の評判
見守りサービスを選ぶ際には、実際の利用者からの口コミや評判が非常に参考になります。広告や宣伝だけでは分からない実際の使用感や満足度などを知ることができ、サービスの信頼性や品質を判断する手助けとなります。
口コミサイトやSNS、知人からの紹介などを通じて、多くのユーザーの意見を集めましょう。特に、長期間にわたりサービスを利用している方のフィードバックは、継続的なサポートや信頼性を確認する上で重要な情報源です。
こうした情報を参考にすることは、自分や家族に最適な見守りサービスを選ぶための有効な手がかりとなります。また、複数の口コミを比較すればより客観的な判断が可能です。
本人の意思をなるべく尊重する
見守りサービスを選ぶ際は、利用者本人の意思を尊重することが何よりも重要です。本人が納得していないサービスを無理に導入すると、ストレスや抵抗感を引き起こす可能性もあります。
サービス内容や機能を詳しく説明し、本人が理解し納得できるまで話し合いを行うことが大切です。また、本人の希望や意向を最大限に尊重すれば、サービスの利用に対する前向きな姿勢が生まれ、長期的な利用にもつながります。
家族やケアマネジャーが協力し、本人が安心してサービスを利用できるようにしっかりとサポートすることが求められます。本人が主体的にサービスを選ぶプロセスを尊重し、信頼関係を築くことが大切です。
専門家に相談する
見守りサービスを選ぶ場合は、専門家に相談することも重要なポイントです。介護福祉士やケアマネジャーなどの専門的な知識と経験を持つプロフェッショナルは、利用者の状況やニーズに最適なサービスを提案してくれます。
特に、家族だけでの判断が難しい場合は、専門家の意見を参考にすることで、より安心して選択を行うことが可能です。また、専門家は最新のサービス情報や地域ごとの支援制度にも精通しているため、より良いサービスを選ぶための幅広い選択肢が得られます。
専門家と協力すれば、利用者本人に最適な見守りサービスを見つけやすくなるでしょう。
まとめ
高齢者の見守りサービスは、高齢者とその家族が安心して暮らすためのサポートをしてくれますが、万が一の際に早急な対応ができない場合も考えられます。万全のサポート体制で安心して暮らしたい方には、高齢者向け住宅に転居するのもおすすめです。
旭化成ホームズが提供する、シニア向け賃貸物件「ヘーベルVillage(ヴィレッジ)」では、安心と安全を実現する24時間365日の駆けつけサービスのほか、相談員による月1回の定期面談や入居者様同士の交流イベントなどもご利用いただけます。高齢者が安心して自分らしい暮らしができる住まいをお探しの方は、ぜひヘーベルVillage(ヴィレッジ)への入居をご検討ください。